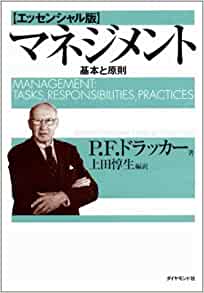ドラッカーのマネジメントの基本と原則シリーズ2:マネージャーの役割と仕事とは?

目次
こんにちは、石井です。
本シリーズのコラムは、「エッセンシャル版:マネジメント基本と原則(ダイヤモンド社 2001年 P・F・ドラッカー著 上田惇生編訳)」を元に、複数回に分けてドラッカーのマネジメントを解説しています。
また、ドラッカースクールを卒業生であり、現在ドラッカー学会理事である藤田勝利氏の著作「ドラッカースクールで学んだ本当のマネジメント(日経BP 2021年)」も参考にします。
本日は、連載の第二回として「マネージャーの役割と仕事」を中心にして、ドラッカーのマネジメントを考えていきましょう。「働きがい」や「人材開発」についても解説しています。
前回の「基本と原則」と「企業の目的」について解説している記事はこちら。
>ドラッカーのマネジメントの基本と原則シリーズ1:企業の目的と機能とは?
マネジメントとは?(再掲載)

「マネジメント」という言葉を聞いて、皆さんはどのようなイメージを持ちますか?また、「マネジメントを日本語で述べてください」と言われたら、どのように回答しますか?
マネジメントの意味
日本のマーケットにおいて、「マネジメント」はさまざまな意味で活用されています。
例えば、マネジメントの派生語であるマネージャーという言葉を考えてみましょう。「マネージャー職」と言えば、「管理職」と同じ意味であることが多いのではないでしょうか。この文脈では、「マネジメント」という言葉は、「管理」という意味で活用されています。
しかし、ドラッカーのマネジメントという文脈では、マネジメントとは「なんとか~する」という動詞で捉える方がしっくりきます。つまり、マネジメントとは何かを生みだす意味合いを含んでいるのです。
「管理」ではなく「創造」
藤田勝利氏によれば、「管理」の英語はコントロール(Control)です。一方、マネジメントとは「創造」の意味を持っているのです。
「ドラッカースクールで学んだ本当のマネジメント(藤田勝利著 日経BP 2021年)」においても、下記の言葉が述べられています。
マネジメントとは人間と創造に関わるものである
管理されすぎると、社員は主体性を発揮しにくくなる
このように、マネジメントとは「管理」ではなく「創造」であり、未来志向で何かを生み出す仕事と言えるのです。
マネジメントは役職ではない
もう1つ強調しておきたいことは、マネジメントは役職ではないということです。では、マネジメントとは何か?藤田勝利氏の言葉によると「誰もが知るべき教養である」ということです。
前述した通り、マネジメントとは「管理」ではなく「創造」です。「創造」とは何かを生み出す仕事です。
つまり、役職とは関係のない事柄です。誰もが仕事をする上で、役職に関係なくマネジメント力を発揮することができるのです。
マネージャーの2つの役割

ドラッカーは、マネージャーは2つの役割を持つと述べています。それは、「創造」と「調和」です。では、それぞれを確認していきましょう。
役割1:創造
組織やチームをマネジメントするマネージャーにとって、大切にしたい思考は「メンバー個々人が持つ能力の総和よりも、組織やチームが生み出す価値を高いものにする」ことです。
ドラッカーは、「メンバーの強みを活かす」ことを強調しています。これは、メンバーそれぞれが持つ弱みをないものにしてしまうほど、強みが結集され組織やチームとして高いパフォーマンスを発揮することの重要性を解説しているのです。
言い換えると、マネージャーの役割の1つは「メンバーの強みを掛け合わせることで、組織やチームの生産性を高いものにすること」と言えるでしょう。
前回のコラムおよび、前章で再掲載した内容に立ち戻ると、マネジメントとは「なんとか~する」という動詞です。これは、何か新しいものを生み出す「創造」に関連していると言えます。
マネジメントとは「何かを創造する仕事」なのです。
役割2:調和
調和とは、直近と長期的に必要であるものをそれぞれ理解し、実践に落とし込むことです。
会社は、定められた期間の中で一定の成果を創出する必要があります。具体的には、週・月・四半期・半期・通期というように短期的なものから、三か年計画のように中期的なものがあります。
マネージャーの役割とは、これらの時間軸が異なる目標を「調和」する必要があるのです。
例えば、営業現場の「決算」を用いて具体的に考えてみましょう。よく決算期では、「割引をしても、とにかく売上を出す方針」がとられます。このような場合に、営業担当者はお得意先をまわり営業活動をします。
確かに、短期的には割引をすることで一定の売上を出すことができるでしょう。ただ、割引した商品やサービスは、次年度以降に販売することが難しくなる可能性があります。また、決算期のやや強引な販売は、お客様との長期的なリレーションに傷をつけるかもしれません。
このようにマネージャーは、短期と長期のジレンマにさらされています。このような状況下で、正しい意思決定をして組織やチームを良い方向に進めなければならないのです。そのためには、「調和」が必要なのです。
マネージャーの5つの仕事

ドラッカーは、マネージャーには「5つの仕事」があると述べています。それぞれを確認していきましょう。
仕事1:目標を設定する
組織やチームをマネジメントすることで、目標を達成することがマネジメントの仕事の1つです。
前章でお伝えしたように、マネージャーはメンバーそれぞれが持つ能力の総和よりも高い価値を創出するような組織やチーム運営をしなければなりません。
目標とは、数字だけで表せるものではありません。
会社の理念やビジョンを実現するために、なぜその定量目標があるものか、また定性的な目標があるのかをメンバーにわかりやすく説明する必要があります。このように、かみ砕いて説明することもマネージャーの仕事の1つなのです。
仕事2:組織する
ドラッカーの「組織する」の真意は、同じチームに属することだけを指しません。これは、メンバーが強みを活かすことができる集合体の意味も含んでいます。
そもそも、「組織する」はOrganize/ Organiseという英語であり、「意図を持って人を集めること」という意味があります。
繰り返しますが、マネージャーの仕事の1つはメンバーの強みを活かし、組織やチームの生産性を高めることです。そのためには、「組織する」ことが必要となるのです。
仕事3:動機づけとコミュニケーションを図る
動機づけは、モチベーションと言い換えても良いでしょう。マネージャーの仕事の1つは、メンバーのモチベーションを高め、それを高い次元に保つことです。
注意しなければならないことは、モチベーションにつながる要因は、メンバーそれぞれ異なるということです。
動機づけに関しては、ハーツバーグの動機づけ理論が有名であり、人は2つの要因によって動機付けされているとしています。
それらは、「衛生要因」と「動機づけ要因」です。詳しくは、元ハーバード大学の教授である故クレイトン・M・クリステンセンの著書「イノベーション・オブ・ライフ」を紹介したこちらの記事が参考になります。
>イノベーション・オブ・ライフ(クレイトン・M・クリステンセン 2012年 翔泳社) 仕事を通して幸せを感じるためのヒント
続いて、コミュニケーションを考えます。コミュニケーション(Communication)とは、日本語では「意思疎通」です。分解して捉えると、マネージャーの仕事の1つは、「意思」を「疎通」することと言えます。
わかりやすく極端な例で捉えると、いくら1on1を遂行しても、マネージャーとメンバーの「意志」が「疎通」していなければ意味がありません。逆に、メール1通でも「意志」が「疎通」すれば意味を成します。
要するに、手段にとらわれすぎずに、マネージャーとメンバーの意思が疎通しているかにフォーカスする必要があるのです。
仕事4:評価測定する
メンバーの仕事を評価することも、マネージャーの仕事の1つです。
マネージャーは、メンバーに責任のある仕事を与え、メンバーがオーナーシップを持った状態で仕事を遂行させます。
そして、それに対して客観的にフィードバックをすることがマネージャーの仕事なのです。評価測定をする際には、事実ベースでのフィードバックが重要となるでしょう。
仕事5:人材を開発する
人材育成の手法は、相当数存在します。その中で、メンバー一人ひとりの個性や特徴に合わせて、マネージャーが育成していきます。
その際に大切なことは、人材育成の手法以前に、マネージャーが「真摯であるか」ということです。真摯とは、愛想が良い事や人付き合いが良い事を指しません。メンバーに対して一流の仕事を要求すると同時に、自分に対しても高い水準の仕事を要求します。
そして、それを実行していきます。マネージャーにとって、「どのように育成するか」を考えることも大切ですが、それ以前に「自分がどのようなマネージャーであるか」という問いも忘れてはならないのです。
※マネジメントに関する研修をまとめた資料は以下からダウンロード頂けます。
マネジメント研修ラインナップの資料ダウンロードはこちら人をマネジメントする上で
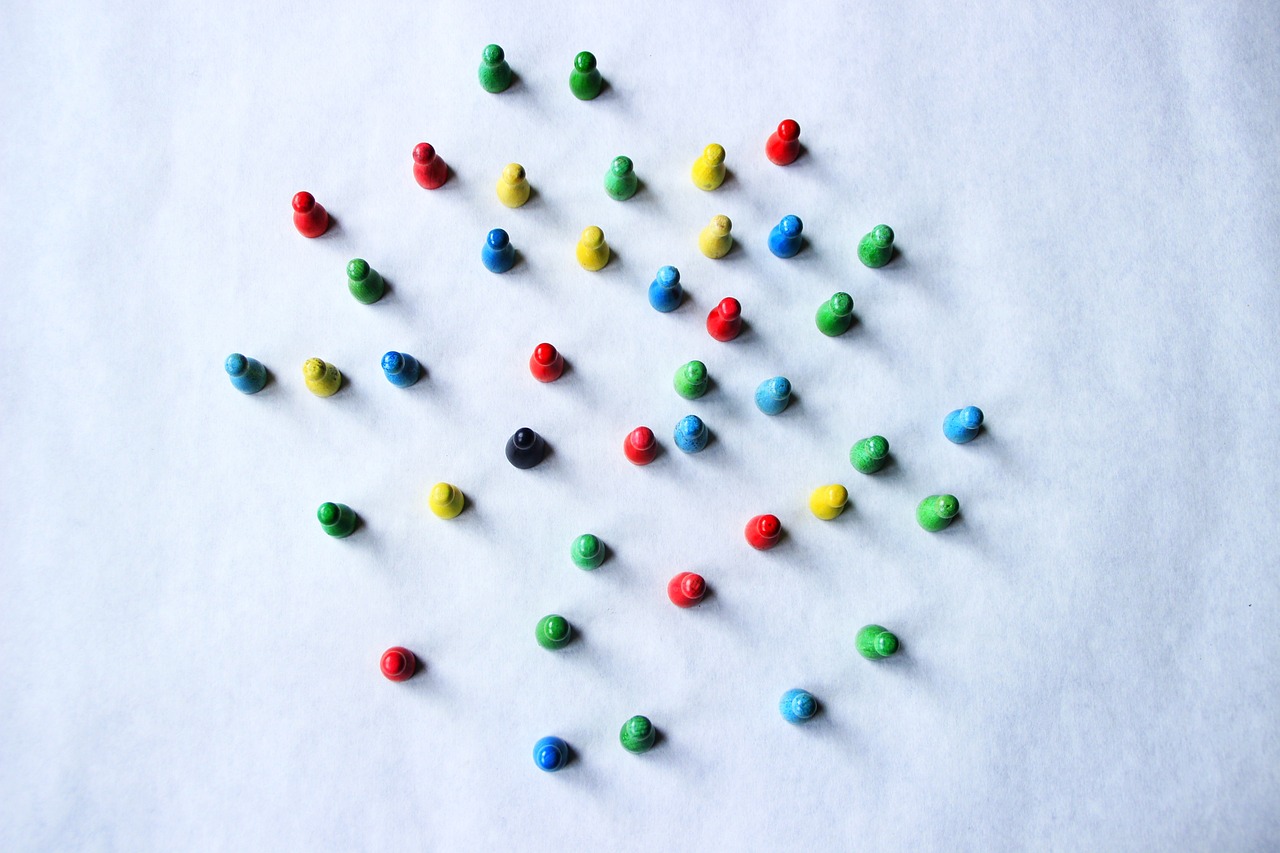
ドラッカーは、会社が持つ資産の中で「人」を特別視していると言えます。具体的には、下記の言葉を残しています。
- 人こそ最大の資産である
- 組織の違いは人の働きだけである
ドラッカーは、資産(建物、土地、オフィス機器、テクノロジーなど)の中でも、なぜ「人」にフォーカスしたのでしょうか?それぞれを考えてみましょう。
人こそ最大の資産である
ドラッカーは、人の強みにフォーカスしたマネジメントの重要性を強調しています。その背景には、人は一人ひとり違ったスキルやマインドを持っていることがあるのではないでしょうか。もちろん、強みも弱みも人それぞれ違うわけです。
ドラッカーは、下記のように語っています。
組織の目的は、人の強みを生産に結びつけ、人の弱みを中和することにある。
人は誰もが弱みを持っていますが、組織となりチームとなることで、それらが中和され、高い価値を創造できる集団になるのでしょう。これこそ、マネジメントの醍醐味と言えます。
組織の違いは人の働きだけである
ドラッカーは「組織の違い」は「人の働きだけ」と強調しています。いくら高い機械や道具を購入しても、結局それを扱うのは人間です。
そして、それらの機械や道具は同じ動きをしますが、人間はそれぞれ異なります。つまり、組織の違いは人間の違いだけなのです。
大切となる価値観
組織で、メンバーの強みを活かし合うために大切なことは何でしょう。それは、互いの価値観を理解することではないでしょうか。
株式会社アルヴァスデザインが提供しているマネジメントコンテンツ(ドラッカー学会理事の藤田勝利氏が監修)では、「価値観」の重要性を強調しています。
具体的には、チームのメンバーが強みを発揮し合うマネジメントをするためには相互理解が不可欠であり、そのためには「価値観」のような深い部分まで互いにわかりあう必要があるのです。
マネジメント研修ラインナップの資料ダウンロードはこちら働きがいの3条件

マネージャーの仕事の1つである「動機づけ」について、「働きがい」という観点でさらに詳しく見ていきましょう。
ドラッカーは、働きがいを与えるためには、仕事そのものに責任を持たせなければならないということを強調しています。その上で、働きがいの3つの条件のそれぞれを見ていきましょう。
条件1:生産的な仕事
生産的な仕事の前に、ドラッカーが大切にしていた言葉であるKnowledge-Worker(知識労働者)を確認しましょう。これは、文字通り「知識によって仕事をする人たち」を指します。
工場で機械が製品を生み出していた産業時代とは異なり、現代の価値の源泉は「知識」にあります。言い換えると、私たちの多くの仕事が知識を中心に価値を創造しているのです。
ただ、忘れてはならないことは、企業の目的(リンク第一回)は、「顧客の創造」であり「知識を活用すること」ではありません。つまり、「顧客の創造」を中心とした目的思考を持つことが生産的な仕事をする第一歩と言えます。
そのためには、知識をインプットすることよりも、顧客志向に立ってアウトプットする意識が必要となります。
条件2:フィードバック
フィードバックとは、マネージャーがメンバーに対して実行する行為です。具体的には、メンバーが創出した成果に対して行われます。
忘れてはならないことは、メンバーの仕事のオーナーシップはメンバーにあるということです。その上で、マネージャーは客観的にフィードバックをしなければなりません。
また、逆にメンバーからマネージャーに対するフィードバックをもらうことも必要です。これにより、組織やチームの運営を軌道修正していく必要があるでしょう。
条件3:継続学習
継続学習とは、Knowledge-Worker(知識労働者)とも強い紐づきがあります。
マネージャーは、自身が学び価値を創造するサイクルを創り出さなければなりません。これによって、メンバーの学習意欲は刺激を受けます。そして、メンバー自身も学び、それによって成果を生み出し、モチベーションにもつながっていくのです。
働きがいの4要素

続けて、働きがいの4つの要素を見ていきましょう。
これは、株式会社アルヴァスデザインが提供しているマネジメントコンテンツ(ドラッカー学会理事の藤田勝利氏が監修)で紹介されています。それでは、1つずつ確認していきましょう。
その1:ビジョンへの共感
会社のビジョンと自身のビジョンが一致することは、働きがいに大きく影響します。メンバーのキャリアビジョンと、仕事内容の関係性を意識することも重要と言えるでしょう。
その2:仕事への貢献実感
メンバーがどの程度、会社や組織の仕事に貢献できているのかを理解することも重要な要素です。メンバーは自身の貢献度を、マネージャーからのフィードバックにより認識し、それをモチベーションに変えることができます。
その3:メンバーとの協働実感
組織やチームは、メンバーの強みを結集することで高い価値を発揮できます。この過程で大切なことは、メンバーで強みを活かし合い、弱みをないものにすることです。これこそが協働する実感であり、モチベーションの源泉の1つなのです。
その4:自身の成長実感
最後に、メンバーそれぞれが成長している実感を持てるかどうかも大切な要素です。これには、マネージャーからのフィードバックが欠かせません。また、メンバーが自身の行動をリフレクションする機会を持つことも大切となるでしょう。
気になる方は、ぜひ、マネジメント研修ラインナップをご覧ください。
マネジメント研修ラインナップの資料ダウンロードはこちら人材育成の勘所

マネージャーの仕事の1つである「人材育成」について、さらに解説していきます。
素質は生まれつきか?
アカデミックなタレントマネジメントの分野において、しばしばNature versus Nurture(自然か?育成か?)という表現が用いられます。これは、素質は先天的に生まれつきのものなのか、後天的に身に付けるものなのかという議論です。
ドラッカーは、下記の言葉を残しており、マネージャーとは開発されるものであるという立ち位置をとっています。
マネージャーは育つべきものであって、生まれつきではない。
裏を返せば、組織は人材を開発することによって、マネージャーを生み出さなければならないのです。マネージャーは勝手に育つわけでもなく、育つまで待つことも無意味です。
また、既に開発されたタレントを中途で採用することも大切ですが、より重要なことは自社でマネージャーを育てる気概を持つことなのです。
実際に、これらを示唆する言葉としてドラッカーは下記を残しています。
マネジメント開発は、人事計画やエリート探しではない。それらのものはすべて無駄である。有害さえある。
いかに、ドラッカーがマネージャーを体系的に育てることが大切であると強調しているかがわかります。
マネジメント開発で大切なこと
ドラッカーは、マネジメント開発をする上で「メンバーの性格を変えることや改造すること」を否定しています。
言い換えると、一人ひとりの強みに合わせた人材開発が重要であるとしています。これは、ドラッカーが繰り返し強調している「強みを活かす」という考えにも大きく通ずるものがあるでしょう。
また、現代社会においては、過去の成功を真似するだけでは良い成果を生み出すことはできません。
そのような文脈で、マネジメント開発も過去の成功者の模倣だけでは成り立たないという現実があります。この観点においても、やはり「強みを活かす」ことが大切なのです。
ドラッカーのマネジメントに関するダイジェスト動画をご覧になりたい方は以下からご希望ください。
マネジマントセミナーの資料ダウンロードはこちらまとめ

いかがでしたでしょうか。
本日は、ドラッカーのマネジメントにおける「マネージャーの役割」と「マネージャーの仕事」を解説しました。また、「働きがい」「人材開発」についても詳しく解説しました。
マネージャーの役割とは、「創造」と「調和」です。マネジメントには、何かを生み出すという意味があります。つまり、マネージャーはメンバーの強みを最大限に活かし、強い組織やチームを作ることで、高い価値を創造しなければならないのです。
また、メンバーのモチベーションを高めることはマネージャーの仕事の1つです。メンバーの働きがいを高い次元に保ち、お客様に高い付加価値を提供することこそが、マネージャーの仕事なのです。
最後に、マネジメント開発は会社にとっても非常に大切な仕事の一つです。将来のリーダーを育てることは、会社の存続につながり、会社の歴史をより良いものにしていきます。これこそが、持続可能な会社と言えるのでしょう。
ドラッカー学会理事であり、「ドラッカースクールで学んだ本当のマネジメント(日経BP 2021年)」の著者でもある藤田勝利氏が監修している株式会社アルヴァスデザインのマネジメントコンテンツはこちらをご覧ください。
マネジメント研修ラインナップの資料ダウンロードはこちらマネジマントセミナーの資料ダウンロードはこちら 資料をダウンロードする お問い合わせをする目次

石井 健博
ブランドマネージャーとして、マーケティングを担当。
営業・リベラルアーツ・マネジメントなどのコラムを発信中。